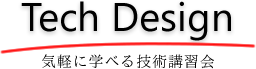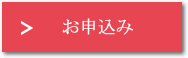 |
|
|
— 現場で効く「基礎→劣化→防止策」を一本の線でつなぐ 食用油脂の基礎と劣化防止
|
|
||||||||||||
|
講師:中谷技術士事務所代表技術士(農業部門)合同会社ノースDXラボCTO 中谷明浩氏 https://nakatani-peoffice.com/大手食用油メーカーでの在籍25年間、生産技術、研究開発、知的財産の各分野で豊富な実績と経験を積む。その後、油脂関連技術と知財情報を専門とする「中谷技術士事務所」を設立。「食用油と知財情報の水先案内人」として、数々の技術課題を解決に導くエキスパート。執筆活動には、食品化学新聞「調理現場のフライ油適正管理技術」(2019年3月21日掲載)、日本食糧新聞・月刊食品工場長10月号「解説・食用油脂の価格高騰と劣化防止策」(2022年10月1日掲載)など、多数を発表。著書に「食用油脂の基礎と劣化防止」(幸書房)がある。また、農林水産食のDXを開発・推進する合同会社ノースDXラボCTO(最高技術責任者)を務める。 |
||||||||||||
| プログラム 1. 食用油脂の基礎知識 2. 食用油脂劣化の基礎知識 3. 劣化防止技術 |
||||||||||||
| 【アジェンダ】 食用油脂は「調味料」であり「素材」です。だからこそ、扱いひとつで風味も価値も変わります。管理を誤れば酸化が進み、青臭・油やけなどのオフフレーバーが生じ、商品の信頼は容易に損なわれます。 解決の鍵は、油を替えるだけではありません。原材料の選択、加熱条件、酸素・光・水分の制御、設備と衛生、そして包装・保管——工程全体の設計です。対症療法ではなく全体をリデザインすることで、品質の安定化・歩留まり向上・返品低減・コスト最適化・ブランド毀損リスクの抑制を同時に実現できます。 本セミナーでは、30年以上“油”と向き合ってきた実務経験にもとづき、原因の見える化(評価指標)→現場で直す → 仕組みにするまでを、現場で実践できる手順としてお伝えします。劣化は管理できる現象です。明日から使える技術と実装の勘所をお持ち帰りください。 第1章:食用油脂の基礎(分類/役割/管理指標/油種特性と用途/製造/微量成分/最新動向) 第2章:劣化の基礎(自動・熱・光酸化/脂肪酸別の酸化性/油種差/促進因子/毒性の見方) 第3章:防止技術(評価指標/基本5項目/衛生管理/適正使用・換油/加熱安定油/抗酸化剤/包装材/脱酸素/寄与成分/劣化臭対策/n-3油の抑制/技術動向) 【1章】脂肪酸組成・物性とおいしさ/食感/歩留まりの関係を説明できる(分類、管理指標、油種特性、製造法、微量成分/最近動向)。
【2章】自動酸化・熱酸化・光酸化の違いと、油種/脂肪酸ごとの劣化特性を言語化し、促進因子を制御できる。 【3章】劣化指標を用いた状態把握、基本5項目にもとづく管理設計、衛生管理との接続、包装・脱酸素・抗酸化・加熱安定油の使い分け、n-3油の劣化対策まで、具体的な手順で実装できる。 R&D/商品開発、品質保証・管理、製造・調理責任者、工場長・スーパーバイザー、原料・包装資材サプライヤー、外食・中食・惣菜の実務者、食品衛生管理担当者 |