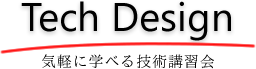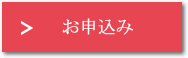 |
|
|
サイエンスカフェ:
|
|
||||||||||||
| 【講義概要】 食品工場における微生物制御はこれまでは一般生菌や大腸菌群を指標菌として構築されることが多かったのですが、今回はセンシティブな離乳食という商品群を製造販売しているという前提に立つことで、本来は何を指標とすべきかを再考するきっかけとしていただきます。製品に入り込まれたら困る、製造工程の中で生き延びられたら困る、(加熱があるときもあればないときもあるが)今から提供という最終調整の後に増えられたら困る、食べ残しがあった場合その保管中に増えられたら困る微生物はなにかという観点から微生物迎撃態勢を全面的に見直してみるという作業を通して真に有効な微生物制御のあり方を模索していただきます。 |
||||||||||||
|
l 微生物の進化
l 医療と食品での微生物分析の差異
l 乳幼児の食中毒の特徴
l 離乳食・幼児食事業者にとっての課題は
l 迎撃態勢の構築
l 規格基準と公定法
l 簡易法と自分なりの工夫
|
||||||||||||
|
【習得事項】 我が国においては、食品の衛生指標として一般生菌、大腸菌群を採用したという愚策のおかげで、工場における微生物対策もまた一般生菌や大腸菌群に傾倒してしまうという無意味な方向に向かってしまっている例があまりにも多くなっています。本来であれば、食中毒を引き起こす微生物を第一義とし、食品の品質を落とす細菌類を第二義の対象としての微生物制御体系をくみ上げていくべきにもかかわらずです。 今回はこの話題を、非常にセンシティブな離乳食・幼児食を販売する企業という仮定の下、皆さまもご苦労なさっているであろう製造委託先での生産の管理もおこなうという条件まで付けくわえてストーリーを展開していきます。一番厳しい条件群を付与することによりストーリーの現実味が増していくばかりか、そんな苦しい中でもソリューションが見つかることを体感していただき、皆さまが自社に戻ってのちに習ったことを実務で応用していく際のハードルを下げることが可能だからです。 食品品質プロフェッショナルズがどのようなセミナーでも申し上げている、1.まず一番怖いリスク群(起こりやすいかつ起こった場合の被害が大きい)を抽出、2.そういったリスクを引き起こす微生物はどこから製品に入り込んでいるのか(微生物がプロセスへのインプットとなってしまっている経路の把握)、3.どこで入り込んでいるかが明確になれば入り込んでいる量のモニタリング、4.微生物を制御しているプロセス(CCP)があるのであれば、そのパフォーマンスのモニタリングという風にまさにHACCPの原点に回帰した手法が微生物制御にとって非常に有効であることを示します。 |
||||||||||||
|
予備知識としてはベビーフード協議会の自主規格https://www.baby-food.jp/standard/pdf/foodkaku6.pdfを閲覧いただき、自分なりのご意見というものを提示いただける状態でお越し下さることを願います。また実際に離乳食・幼児食またはそれに類似する商品を製造販売なさっている企業から参加の方々には実際にどのようなトラブルやニアミスが起きているかを(社外秘に触れない範囲で結構ですので)開示いただけることを望みます。もし開示いただけるのであればセミナー参加以前に講師の広田teddyhirota@yahoo.co.jpに連絡をお願いします。事前に連絡いただけましたら講師も周到な準備をして実際例の紹介やQ&Aに臨むことが可能です。
|