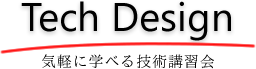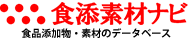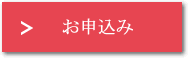

※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
製品開発及び製造工程(原料の粉砕・造粒・乾燥・混合・打錠)の基礎知識とトラブルシューティング、スケールアップの進め方など、食品素材を錠剤・カプセル化する際に押さえておくべきポイントを実務的な観点から解説します。
食品における錠剤・カプセル剤の開発・製造の実務ポイント
~各工程の基礎知識とトラブル対策、サプリメントとしての製剤化とスケールアップの考え方~ |
| コード | tds20250807t1 |
|---|---|
| ジャンル | 食品 |
| 形式 | 対面セミナー(配信あり) |
| 日程/時間 | 2025年 8月 7日(木) 10:30~17:00 |
| 会場 | |
| 配信について | 録画配信期間:8/10~8/30 |
| 資料(テキスト) | 会場受講:当日配布します。 録画配信受講:印刷物を郵送します。 |
| 受講料 (申込プラン) |
会場受講+録画配信受講: 39,600円 (消費税込) 録画配信受講: 39,600円 (消費税込) |
|
|
秋山錠剤株式会社 品質保証部 製剤開発課 顧問 理学博士 阪本 光男氏 ・エーザイ株式会社製剤研究室に入社、ジェネリックメーカ、一般薬メーカの製剤研究室室長を経て、現職・所属学会:日本薬学会 |
|
Ⅰ.製品開発の基礎知識と食品の粉砕から造粒工程におけるポイント |
|
|
【習得知識】 |