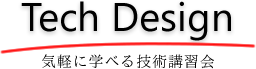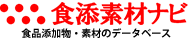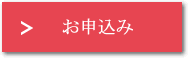

※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
機能性表示食品の届出の一連の実務に関する様々なノウハウを、ガイドラインだけでは理解しきれない部分をフォローしながら2日間で網羅し解説します。1日目はガイドラインの解釈と資料作成のノウハウを、2日目は届出において障害となりやすい各項目の詳細を講義します。
機能性表示食品の届出ノウハウ
~ガイドライン対応/届出資料作成/新規機能性成分の捉え方/定性・定量分析方法/作用機序考察/ヒト臨床試験計画/査読付き論文のまとめ方/システマティックレビュー/事後チェック指針~ |
| コード | tds20250717h1 |
|---|---|
| ジャンル | 食品 |
| 形式 | オンラインセミナー(Live配信) |
| 日程/時間 | 7月17日(木)-18日(金) 10:30~16:30 |
| 配信について | 見逃し配信もあります(視聴期間は講習会当日の10日後まで) |
| 資料(テキスト) | 電子ファイルをダウンロード |
| ご案内事項 | ※本講座ではお申し込み時にご所属の明記を必須事項としております。 講師のご同業者様のお申し込みはお控えください。 |
| 受講料 (申込プラン) |
通常価格: 60,500円 (消費税込) ※基礎編・応用編の2日間受講 基礎編のみ(7/17)の受講: 36,300円 (消費税込) 応用編のみ(7/18)の受講: 36,300円 (消費税込) |
有限会社健康栄養評価センター 代表取締役 柿野 賢一氏 1989年 九州大学 農学部 畜産学科 卒業後、医薬品非臨床試験受託研究機関(GLP機関)入社。2001年に健康栄養評価センターを創業、2004年に法人化し、代表取締役に就任。ほか、株式会社鹿児島TLO(鹿児島大学技術移転機関)アドバイザー、九州大学百周年記念事業推進会 役員(理事)、鹿児島大学理学部 非常勤講師、島根県「島根県産業技術センター」の機能性食品素材研究指導などを歴任。また、健康生きがい学会 役員(理事)、ナチュラルメディシン・データベース研究会 コーディネーター、健康食品・サプリメントの健全な市場流通を考える会 発起人、福岡県機能性食品開発相談窓口事業 窓口業務及び福岡バイオ産業創出事業アドバイザー、公益財団法人 食品流通構造改善促進機構「機能性表示食品セミナー・相談会」の専属講師、公益財団法人みやぎ産業振興機構 専門家を兼任する。著書に【機能性食品表示への科学的なデータの取り方と表示出来る許容範囲「食品の機能性表示を低コストで実現するシステマティックレビューの基礎と事前準備の進め方」(技術情報協会 2015)】【脳・心・腎血管疾患クリニカル・トライアルAnnual Overview2018「機能性を表示する食品のエビデンスと信頼性」(ライフサイエンス出版 2018)】ほか多数。 |
|
|
<習得事項> |
|
|
<プログラム> |
|
|
<講義概要> |
|
|
<プログラム> |
|
|
<講義概要> |