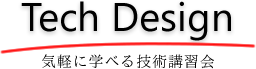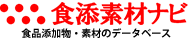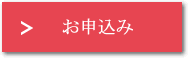

※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
発想から特許査定に至るまで、講師の権利化事例を使って、J‑PlatPatの画面操作や生成AIのプロンプト入力などのデモ形式で実務ノウハウを伝授。
J-PlatPatと生成AIのデモで体感する食品特許の作り方
|
| コード | tds20251215k1 |
|---|---|
| ジャンル | 知財 |
| 形式 | オンラインセミナー(Live配信) |
| 日程/時間 | 2025年 12月 15日(月) 14:00~16:30 |
| 配信について | 見逃し配信もあります(視聴期間は10日程度) 当日の受講が難しい場合は見逃し配信をご利用ください。 |
| 資料(テキスト) | PDFデータのダウンロード |
| 受講料 (申込プラン) |
通常価格: 19,800円 (消費税込) |
福島綜合特許事務所 所長、神戸大学 客員教授、弁理士 福島 芳隆氏 大塚化学(株)にて有機合成、新規農薬の研究開発に従事。退職後、特許庁・審査官として化学分野の審査に従事。その後、大手特許事務所の主任弁理士を経て2016年1月に福島綜合特許事務所を設立。2016年~神戸大学 知的財産マネージャー(非常勤)、産官学連携本部 客員教授を歴任。食品、医薬、農薬、化粧品等の化学全般が専門。「産、官、学」の全てを経験した弁理士という強みを生かし、技術者・研究者に対して、発明の初期段階から権利化商品化に至るまで、強い特許の取得方法、特許調査、研究開発支援等、幅広い綜合的な知財経営支援を行っている。 |
|
1.はじめに |
|
|
【習得できる知識】 |