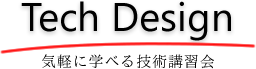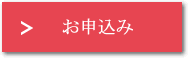

※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
日本国内でも馴染み深いタンパク源の一つである大豆タンパクについて、組成の特徴からゲル化・乳化機能や生体調節能機能、その他応用例までを紹介します。大豆を用いたプラントベースの商品開発をお考えの方の一助になる講座です。
大豆タンパク質の組成・機能性と食品素材としての応用方法
|
| コード | tds20260213z1 |
|---|---|
| ジャンル | 食品 |
| 形式 | オンラインセミナー(Live配信) |
| 日程/時間 | 2026年 2月 13日(金) 15:00~17:00 |
| 配信について | 見逃し配信あり(視聴期間は10日程度) 当日の受講が難しい場合は見逃し配信をご利用ください。 |
| 資料(テキスト) | 電子ファイルをダウンロード |
| 受講料 (申込プラン) |
通常価格: 24,200円 (消費税込) |
元茨城大学 農学部 客員教授 佐本 将彦先生 不二製油㈱にて、主に大豆タンパク質をベースにした食品素材開発に従事。京都大学特任教授、茨城大学客員教授を経て、2024年9月退社。著書:「大豆のすべて」サイエンスフォーラム、「豆類の百科辞典」朝倉書店 など |
|
Ⅰ.タンパク質の基本的な内容 |
|
|
<習得知識> |