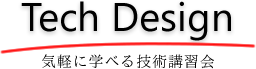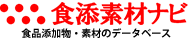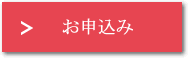

※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
製品のどのような位置にどのようなメカニズムで“応力集中”が発生し、どの点に注意すればいいのかを豊富なCAE解析(シミュレーション)事例と研究事例を参照しながら解説します(配布スライド300枚以上)
CAE解析と応力集中部の評価
~CAE解析の“正しい読み解き方”と応力集中のメカニズム理解~ |
| コード | tds20250729a1 |
|---|---|
| ジャンル | 機械 |
| 形式 | オンラインセミナー(Live配信) |
| 日程/時間 | 2025年 7月 29日(火) 10:00~17:00 |
| 配信について | 見逃し配信あり(視聴期間は10日程度) 当日の受講が難しい場合は見逃し配信をご利用ください。 |
| 資料(テキスト) | PDFデータの配布(ダウンロード) |
| 受講料 (申込プラン) |
通常: 36,300円 (消費税込) |
|
|
九州工業大学 名誉教授 野田 尚昭先生 専門は材料力学・弾性力学で、特に「切欠きやき裂を有する強度研究用試験片等の体積力法による応力解析」に従事。最近では、CAEを利用した企業との共同研究・受託研究の依頼を受けることが多くなってきており、それらが研究の中心となっている。公表された論文は300件以上。素形材産業技術賞素形材センター会長賞(2010年)、日本材料学会学術貢献賞(2010年)などを受賞。著書には、『演習問題で学ぶ釣合いの力学』(コロナ社、2011年)、『設計者に活かす切欠き・段付き部の材料強度』(日刊工業新聞社、2010年)、『設計者のためのすぐに役立つ弾性力学』(日刊工業新聞社、2008年)、『Q&Aでわかるリスクベース設計のポイント』(日刊工業新聞社、2006年)などがある。日本機械学会、自動車技術会、日本材料学会、鉄鋼協会、塑性加工学会などに所属。 |
|
0.CAEによる応力解析とはそもそもどのようなものか |
|
|
<習得事項> |