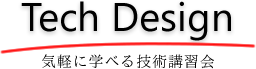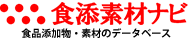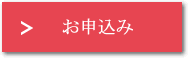

※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
食品技術者のために香気の本質的な理解から解析方法の実践的な内容までを解説する講座を新設しました。本講座では、有機化学的視点からにおい分子を理解し、複合臭の構造や解析手法を解説。GC-MSの活用や官能評価の工夫も取り上げ、実際の食品素材を例に科学的に香気を捉えるヒントが満載です。現場に活かせる知識が得られます。
食品香気の科学的理解と複合臭解析方法
|
| コード | tds20251217t1 |
|---|---|
| ジャンル | 食品 |
| 形式 | 対面セミナー(配信あり) |
| 日程/時間 | 2025年 12月 17日(水) 13:30~15:30 |
| 会場 | |
| 配信について | 【見逃し配信】はありませんので、ご注意ください。リアルタイムでのご受講をお願いします。 |
| 資料(テキスト) | 対面受講:当日配付+データのダウンロード オンライン受講:データのダウンロード |
| ご案内事項 | ※対面受講者は講義終了後に個別相談、個別解説の時間を1時間30分程度取ります。(任意参加) オンデマンド講座を追加で受講するとお得になります。(合計55,000円で受講可能) におい分子で捉える“複合臭”とその解析・評価技術 におい素材の分析 データ解釈の仕方、におい特徴の捉え方 いつでも受講できるため予習に使っても復習に使っても問題ありません。 |
| 受講料 (申込プラン) |
オンライン受講: 27,500円 (消費税込) オンライン受講会場受講+オンデマンド講座(におい分子で捉える“複合臭”とその解析・評価技術 + におい素材の分析 データ解釈の仕方、におい特徴の捉え方) : 60,500円 (消費税込) 会場受講: 27,500円 (消費税込) 会場受講+オンデマンド講座(におい分子で捉える“複合臭”とその解析・評価技術 + におい素材の分析 データ解釈の仕方、におい特徴の捉え方) : 60,500円 (消費税込) |
埼玉大学 シニアプロフェッサー 長谷川 登志夫先生 1983年 東京大学大学院理学系研究科有機化学専攻修了。埼玉大学理学部基礎化学科助教授などを経て、2007年より埼玉大学大学院理工学研究科助教授。また2014年より埼玉大学研究機構脳末梢科学研究センター兼任教員。2023年より現職。日本古来の香気素材の香気プロフィールの解明、特徴的香気を有する化合物の構造と香りの関係の解明、新規香気解析手法を用いたお茶、日本酒、木材など種々の香気素材の香気と特性の検討などの研究を行っている。 |
|
1.においの科学の分子レベルでの理解 |
|
|
<習得知識> |