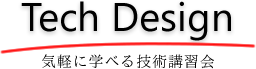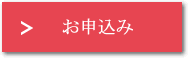

※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
技術者としての長年の経験と、社内外の文書作成、添削指導を行ってきた講師の実績をもとに、技術文章を書く上での基本スキルと文書作成のポイントを豊富な添削事例の提示と演習を交えてわかりやすく解説し、生成AIの効果的な利用を含めて説明します。
わかりやすい「技術文書の書き方」講座
~基礎から生成AI活用まで~ |
| コード | tds20260220a1 |
|---|---|
| ジャンル | 汎用(ビジネススキル) |
| 形式 | オンラインセミナー(Live配信) |
| 日程/時間 | 2026年 2月 20日(金) 10:00~16:30 |
| 配信について | アーカイブ配信なし(リアルタイムでのご受講をお願いします) |
| 資料(テキスト) | 印刷・製本したものを郵送 |
| 受講料 (申込プラン) |
通常: 36,300円 (消費税込) |
|
|
小波技術士事務所 工学博士/技術士(機械部門) フルード工業株式会社 執行役員 技術開発室長 小波 盛佳氏 横浜国立大学大学院(化学工学専攻)修了後、日曹エンジニアリング㈱で粉体物性解析、機器の開発、粉体プラントのプロセス設計・プロジェクト、制御システム開発・設計や、半導体関連の設備・装置の開発・設計に従事。その後、新規事業開発リーダー、技術開発研究所長として大学・企業と提携し装置等の開発に携わる。現在は、機械・設備の解析・コンサルタントを行う一方、大学の授業、技術者向けの粉体技術、技術文書法、技術発想の各セミナーで講義する。月刊「粉体技術」誌の編集委員(36年間)、専門の著作190点余、講演360件余。横浜国立大学・千葉大学非常勤講師、鹿児島大学客員教授、立上げベンチャーの取締役などを歴任し、鹿児島大学非常勤講師、日本創造学会研究倫理委員長、技術士(機械部門)、工学博士。 |
|
1.文書作成の心構え |
|
|
【習得知識】 |