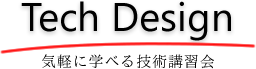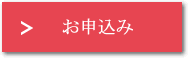

※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
衛生確保に不可欠な細菌検査について、微生物とその中毒の基礎知識に加え、実務ノウハウと食中毒・事故を予防するポイントを解説! 検査担当者はもちろん、現場従事者や設備担当者も押さえておくべき衛生・HACCPの知見や原因細菌の検査法についても講義します。
食品製造における微生物学の基礎と検査の実務ノウハウ
~微生物学の基礎 / 無菌操作 / 培地作成 / 標本作製 / 分離 / 培養 / 保存 / 実地の検査~ |
| コード | tds20260212h1 |
|---|---|
| ジャンル | 食品 |
| 形式 | 対面セミナー |
| 日程/時間 | 2026年 2月 12日(木) 10:30~17:00 |
| 会場 | |
| 資料(テキスト) | 印刷物を配布いたします。 |
| ご案内事項 | ※その他、微生物検査でお困りの事柄などございましたら事前にご連絡ください。 可能な限り講師より知見をご紹介いただきます。 |
| 受講料 (申込プラン) |
通常価格: 39,600円 (消費税込) |
|
|
自治医大 非常勤講師 滝 龍雄氏(元 北里大学) 略歴:1973年 北里大学大学院修士課程修了後、自治医科大学 医学部を経て北里大学 医療衛生学部 准教授。2014年 北里大学を退職後、現職。自治医科大学、さいたま看護専門学校にて非常勤講師を務める。教育:微生物学(臨床/環境)の講義・実習 研究:・易感染性宿主における細菌感染に対する抵抗性の増強について・消毒薬を用いた食中毒起因菌の抑制について ・殺菌抵抗性セレウス菌の消毒薬抵抗化の機序について所属学会:アメリカ免疫学会(AAI) |
|
はじめに |
|
|
<本講座での習得事項> |